指定文化財の検索
文化財の概要
文化財名称
上三原の田植ばやし
文化財名称(よみがな)
かみみはらのたうえばやし
市町
萩市
指定
県
区分
民俗文化財
一般向け説明
この踊りの起源は明白ではないが、関ヶ原の戦いの後、益田氏が、この地に移された時に、移住した農民が伝えたものと言われている。この地方の小作人たちが、地主の田植えをする時に、豊作を祈願するために踊ったもので、秋の祭礼には、その初穂を氏神に供えた。一時、中断されたが、明治の末頃に、氏神の神穀田の植え付けの際の芸能として復活した。歌の中に、安芸(現在の広島県)・石見(現在の島根県)系の唄を正しく歌っている部分があり、昔は、安芸・石見系の田植え唄の歌い方と同じであったのではないかと考えられている。
小学生向け説明
1600年(慶長 2)の関ヶ原の戦いの後、益田氏が、この地に移された時、一緒に移り住んだ農民が伝えたものと言われています。この地方の小作人たちが、地主の田植えをする時に、豊作を祈るために踊ったもので、秋の祭礼には、その年に初めてとれた稲穂を氏神に供えました。一時、中断されましたが、明治の末ごろ、氏神の神穀田(神に差し上げる稲を作る水田)の植え付けの時に行う芸能として再び行われるようになりました。
文化財要録
要録名称
上三原の田植ばやし
指定区分・種類
無形民俗文化財
指定年月日
昭和51年3月16日 (山口県教育委員会告示 第3号) 無形民俗文化財
所在地
萩市
保持者
上三原の田植ばやし保存会
時期及び場所
時期・場所ともに不定。
由来及び沿革
この芸能の起源は明白ではないが、益田氏が関ケ原の戦の後、この地に移封された折に移住した百姓が伝えたものといわれている。この踊は、当地方の小作人たちが地主の田植を行なう際に豊作を祈願したものであり、秋の祭礼にはその初穂を氏神に供えた。
途中で一時、中断されたが明治の末葉に氏神の神穀田の植付けの時の芸能として復活した。
内容
囃しの種類は「綾」と称する道行きの囃しと、玉ごし、さねくり、打ち上げの植調子の三種類、都合四種類の囃しか方がある。この中、道行きの「綾」と最後の「打ち上げ」は「ユリ唄」である。
胴の「ばち」さばきは、数種類に分けられており複雑な「代かき」の様子を演じたものであるといわれる。
構成
大胴・シメ胴・拍子・シロかき・えぶり・早乙女の各役割りがあり、出場人員に制限はない。
設備・衣装・用具
(1)衣装
ゆかた・花笠・たすき(5色)・面
(2)用具
下げ杖・ささら・男根・風呂鍬・松葉・ナエメゴ・天秤襷
音楽
楽器は大胴・合鉦・拍子木。
歌詞
本田ばやし前唄 エーひと調子植えよじゃなあいか
エーひと調子植えよじゃなあいか
エーイエイヤアレコラ植えよじゃなあいか
本田はやし唄 清盛と云う人は世に名を残した
清盛と云う人は世に名を残した
兵庫の築島と音戸の瀬戸を開いた 今日植える田主さのやかた眺むれば
今日植える田主さのやかた眺むれば
八つ棟の蔵を建てたやかた眺むれば 面白い声がするあれは何の肥ら
面白い声がするあれは何の肥ら
恵美須大黒の俵まくる声じゃの 日は暮れるゆくや御前駒はどこに繋いだ
日は暮れるゆくや御前駒はどこに繋いだ
尾を越し谷を越しさんがり松につないだ 桃色の玉ぶさを桐の箱に入れての
桃色の玉ぶさを桐の箱に入れての
思う様にまいらせよと桐の箱に入れの きのうまでは友達今日は殿子なられた
きのうまでは友達今日は殿子なられた
せどの山の青しばが燃え立つ程に思へど 沖の瀬の泊り船はあれはどこの船やら
沖の瀬の泊り船はあれはどこの船やら
金の幕に打たれたう越後様の船じゃろ 馬乗りが三人通るどれがうちのむこやら
馬乗りが三人通るどれがうちのむこやら
じまん錦ぢ紫き小刀差したがそうじゃけ 面白いものぞや富士の巻狩りはの
面白いものぞや富士の巻狩りはの
弓矢を揃ろえて富士の巻狩りはの 笠のはが揃ろたよ何笠が揃ろうた
笠のはが揃ろたよ何笠が揃ろうた
京笠に伊勢笠に東笠が揃ろうた 宮島様の御ふしんにはどなたが棟領なされた
宮島様の御ふしんにはどなたが棟領なされた
日田がたくみに武田がばんじょう両主が棟領なされた 以下略
本田はやし〆唄 エーゆりかけ早いが駒よ
エーゆりかけ早いが駒よ
エイーエイヤーこりゃ早いが駒よ エー清盛りゃ夕日をまねく
エー清盛りゃ夕日をまねく
エイエイヤーこりゃ夕日をまねく 以下略
ハー ウッサァ ウッサァ ウッサッサ・・・・・・・・・・・…
特色
上三原の「田植ばやし」を見て、一つの発見ともいえることは「打ち上げ」のユリ唄は、正しくは安芸・石見系のオロシの部分を歌っているということである。オロシを伴わぬことが山口県内の<5,5,6,4,5,5,6,4型>田唄の特徴といわれていたものを上三原ではそのオロシを今なお歌っており、往昔は安芸・石見系の田唄の唱法と同一のものであったろう。
画像



〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
Tel:![]() Fax:
Fax:![]()
E-mail: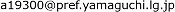
Copyright(C) 2010 山口県観光スポーツ文化部文化振興課
